まず、最初に取り上げたいのは将棋を指す人間が将棋をどのように捉えているかという点である。すなわち、同様に将棋を覚えても興味を示す人もいればそうでない人もいる。それは一体どのような理由によるものなのであろうか。
我々が将棋を指すようになるきっかけは、父親をはじめとする家族もしくは友人に教わってというのが一般的である。教わった当初は指していても、その後ずっと続ける人とそうでない人へとやがて分かれていく。つまりそれは将棋の持っている特徴に魅力を感じる人とそうでない人が存在しているからである。では、将棋を指す人は、将棋のどこに魅力を感じているのであろうか。その理由は、将棋の本来持っているゲームとしての性格に求めるのが適切だろう。そこで、将棋のゲームとしての特徴と絡めながら述べてみよう。
プレイヤーが将棋を面白いと感じるのは、どのような点であろうか。 どのような点で将棋を面白いと感じているかについて、京都大学の将棋部員16人に与えられた選択肢の中から複数回答で回答してもらった結果を回答数の多かったものから順に並べたのが、
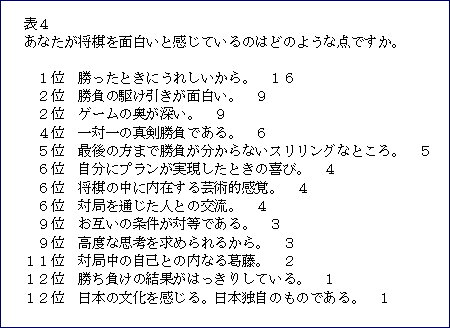 表4のデータである。ちなみに選択肢の右にある数字は回答数である。このデータを見ると、第一位が「勝ったときにうれしいから」となっていて、全員がこの理由を挙げている。すなわち、将棋を指していてもっとも面白いと感じるのは勝った時の喜びなのである。また、二位以下は順に「勝負の駆け引きの面白さ」、「ゲームの奥が深い」、「一対一の真剣勝負である」となっている。これらの項目は、第一章で述べたような将棋のゲームとしての性格に基づくものである。また、その他の「最後まで勝負が分からないスリリングなところ」・「自分のプランが実現したときの喜び」・「お互いの条件が対等である」・「高度な思考を求められるから」といった項目もゲームとしての性質に起因しているものであり、将棋のゲームとしての性格に魅力を感じていることが分かる。
表4のデータである。ちなみに選択肢の右にある数字は回答数である。このデータを見ると、第一位が「勝ったときにうれしいから」となっていて、全員がこの理由を挙げている。すなわち、将棋を指していてもっとも面白いと感じるのは勝った時の喜びなのである。また、二位以下は順に「勝負の駆け引きの面白さ」、「ゲームの奥が深い」、「一対一の真剣勝負である」となっている。これらの項目は、第一章で述べたような将棋のゲームとしての性格に基づくものである。また、その他の「最後まで勝負が分からないスリリングなところ」・「自分のプランが実現したときの喜び」・「お互いの条件が対等である」・「高度な思考を求められるから」といった項目もゲームとしての性質に起因しているものであり、将棋のゲームとしての性格に魅力を感じていることが分かる。
「勝負の駆け引き」や「ゲームとしての奥の深さ」も高く評価されており、このことから、ゲームとしての完成度が評価されているともいえるだろう。また、「一対一の真剣勝負である」点も評価されているいて、第一章で述べた格闘技と共通する要素があるのかもしれない。また、自分のプランの実現・高度な思考という点からは、知的ゲーム・戦略ゲームとしての性格が窺える。そして、将棋特有の性質であると第一章で述べた「最後の方まで勝負が分からないスリリングなところ」が評価されていて、これも興味深いところである。さらに互いの条件が対等であることが、こうしたゲームとしての評価を支えていると言えよう。
その他の魅力の一つとしてあげられる「日本文化を感じさせる・日本独自のものである」という点は、ほとんど評価されておらず、ゲームとして受け入れている側にとってはあまり関係がないようである。将棋は各国において異なった形で存在し、そのため、外形・ルールのなかにその国の文化を色濃く示すものとなっているが、そのことによって生まれている文化的な特徴は愛好している側にとって、あまり関係のないことが分かる。むしろ、結果として生まれたゲームの上での性質の違いに意味があると考えるのが適当だろう。しかし、「将棋の中に内在する芸術的感覚」が評価されており、芸術的な要素が日本人の美意識のに受け入れられていることは、日本文化としての要素が受け入れられていると考えることもできる。芸術的感覚は、将棋をある程度理解してはじめて感じられるものであり、興味の理由とはなりにくいものだといえよう。もう一つ忘れてはならないのは、「対局を通じた人との交流」である。将棋では、勝負の条件は対等であり、社会の枠組みを超えて人と付き合うことができる。そして、将棋という共通の基盤を持っているために交流を深めることができるのである。ただ、この点については将棋を続けている結果として派生的に生まれてくるもので、将棋を指す直接の理由にはならないように思われる。
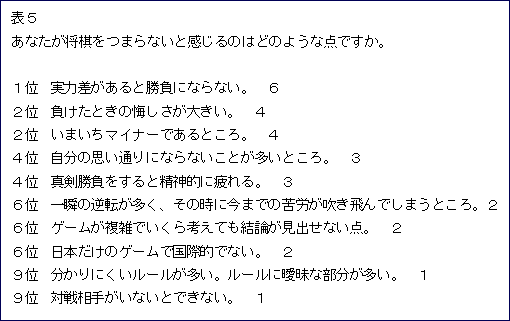 逆に将棋をつまらないと感じるのはどのような点であるかについて、まったく同じ方法で調査をした結果が表5である。表5データを見ると、第一に挙げられているのは、「実力差があると勝負にならない」という点である。これは、将棋が偶然性を排したゲームでプレイヤーの力量のみに依存するゲームであることを間接的に示しており、また、それがゆえの短所である。「負けたときの悔しさが大きい」という点も二番目に挙げられており、逆に勝った時の喜びも大きいことを示していて、将棋が持つ勝負の厳しさとゲームとしての面白さを表しているともいえよう。また、同じく二番目に「いまいちマイナーであるところ」が挙げられ、将棋が遊び全体からするとマイナーにとどまっている現状を将棋を指している人自身が認識していることを示している。実際、趣味の多様化した現在にあっては、将棋の位置は相対的に低下していることは否定できないだろう。
逆に将棋をつまらないと感じるのはどのような点であるかについて、まったく同じ方法で調査をした結果が表5である。表5データを見ると、第一に挙げられているのは、「実力差があると勝負にならない」という点である。これは、将棋が偶然性を排したゲームでプレイヤーの力量のみに依存するゲームであることを間接的に示しており、また、それがゆえの短所である。「負けたときの悔しさが大きい」という点も二番目に挙げられており、逆に勝った時の喜びも大きいことを示していて、将棋が持つ勝負の厳しさとゲームとしての面白さを表しているともいえよう。また、同じく二番目に「いまいちマイナーであるところ」が挙げられ、将棋が遊び全体からするとマイナーにとどまっている現状を将棋を指している人自身が認識していることを示している。実際、趣味の多様化した現在にあっては、将棋の位置は相対的に低下していることは否定できないだろう。
以上の結果を見ていくと、将棋を指している人が感じている将棋の魅力は、やはり将棋の持っている本来の性格によるものだということができる。将棋は、メンタルな部分での勝負の駆け引きはあるものの基本的に思考能力に依存している。したがって、この点に人は魅力を感じるわけであるが、勝負の厳しさがあるため、それになじめない人にとってはつまらないものである。実力がないと勝てないために強くならないとその面白さを実感しにくいゲームであるといえよう。また、思考のプロセス自体にもその面白さは存在している。考えるということに楽しさを見出せるかどうかも面白いと感じるかどうかの分かれ目となるのではないだろうか。
では、将棋を愛好する人は、日頃どのように将棋と接し、また、将棋を楽しんでいるのだろうか。第三章で述べたように将棋を楽しんでいる人の多くは実戦を通じて楽しんでいる。しかし、その相手や頻度・熱心さは人によって様々である。将棋を指すのを趣味として、たまに友人・知人と指したりして気軽に楽しんでいる人たちもいれば、将棋に対してある程度真剣に取り組み、アマチュアの大会などに出場し好成績を挙げることを目標にしている人たちもいる。
いずれの層の人たちもその相手は様々であり、その相手は、友人・知人、学校や職場のクラブ・同好会の人、将棋道場の人であったりする。ただ、将棋のゲームとしての性格上、実力に見合った相手と対局する必要があり、レベルの高い人ほど対局相手を探すのは難しく、そうした強豪クラスが集まりやすい将棋道場などで腕を磨くことになる。ただ、実戦をこなすだけでは実力の向上につながらない。実力の向上をはかるためにはプロの棋譜を並べたり、定跡を勉強したり、詰め将棋を解くなどの努力が必要である。特にアマチュアのトップクラスで実績を挙げるには、かなりの努力が必要でそうした人の場合多くの時間を将棋に割くことになる。もっとも熱心さは実力に比例するものでもなく、実力に関係なく将棋に強い興味を持っている人も存在している。
また、定跡を研究する、プロの棋譜を並べる、詰め将棋を解くなどの活動や、戦形別にデータ収集する1、テレビなどを通じて観戦する、将棋の世界の動き、特にプロの将棋を鑑賞するなどの実戦以外の活動も興味の対象となっている2。例えば、将棋の決まった指し方としての定跡の勉強は、その勉強によって得た成果を実戦で用いることに意味があり、それがうまくいった場合には努力が報われた結果として喜びも格別なものとなる。しかし、実戦を離れて定跡自体の奥の深さに興味を持ち、実戦で使うことを目的としないのに定跡を研究すること自体が趣味になってしまうのである。
一方、詰め将棋の世界はやや特殊で、完全に独立した世界として存在している。詰め将棋は、パズル的な要素を多分に持っており、ゲームとしての将棋とは一線を画すものである。そのため、創作を趣味とする人が多く存在し、互いに作品を発表しあって、評価し合う独自の世界を構成している。彼らの間では、詰め将棋の難解さであったり、奇抜さや盲点を突く面白さについて、独自の美意識に基づいた芸術性の評価が行われているのである。詰め将棋の世界は、一定のファン層を持っており、専門の雑誌が発行されているし、詰め将棋の愛好者の会合もしばしば行われている。このレベルまで到達すると将棋という枠で考えるよりは、一つの知的パズルとして独立した存在になっているといえよう。
また、プロの棋譜を並べるだけとか戦形別にデータ収集したり、将棋界の情報を収集したり、観戦したりするだけの実戦から離れた楽しみ方に興味を示す人たちの存在の見逃せない。例えば、野球の世界で野球観戦だけを楽しむ人と自分で草野球をやるのを楽しむ人がいるように、実戦をこなすというより、プロの将棋界の動きや対局の観戦を楽しむファンがいるわけである。本来、こうした楽しみ方は、実戦を楽しむ人が付随的に楽しんでいたものなのであるが、こちらの方にのみ興味を持ち、一部にはマニアックになる人たちもいる。こうした実戦から遠ざかる将棋ファンは近年増えており3、その楽しみ方はゲームとして将棋を楽しむこととは違ったものになっている。すなわち、こうした人たちにとって、将棋のゲームとしての面白さは副次的なものであって、将棋の持つ知的なゲームとしてのイメージであるとか、プロ棋士達のキャラクターの魅力が、将棋の魅力になっていると考えられる。つまり、将棋の持っている雰囲気だとかイメージの方に意味があるといえるだろう。このケースではマニアックになる方向性とは逆に、こうした雰囲気やイメージにひかれてなんとなく将棋に興味を持ったり、特定のプロ棋士のファンとなるような人も見られる。
こうした実戦以外の楽しみ方の対象の一つとして、プロの世界の存在は重要である。いつの時代にも存在しているスター性を持って活躍するプロ棋士達の姿は魅力的であるし、また、プロの指す将棋はその技術に裏打ちされレベルが高く、見る者を感動させる。そして、それらの魅力をメディアが伝えている。特に現在における羽生ブームなどには、メディアが大きな役割を果たしたということができよう。その中で、実戦を中心に楽しむことが原則だった将棋の楽しむ方が変化していったと言えよう。つまり、将棋が、従来の実戦を通して楽しむだけのゲームから、見せる要素を持ったゲームへと変化してきていると言えるかもしれない。しかし、一方で次のようにも考えることもできる。すなわち、彼らが対局以外のものに関心を示すのは、対局をするには相手を見つけなければならないことが、彼らにとって煩わしいものに映るからであり、同時に、将棋の本来の面白さであるはずの勝負の厳しさが敬遠されているとも考えられる。
このように将棋には、実戦だけの楽しみ方だけでなく様々な楽しみ方が存在している。人によっては、実戦以外の方に興味の焦点を向ける場合があり、将棋が長年の歴史の中で定着し、その歴史の結果として生まれたプロ組織は人々の興味の対象となりうるほどになったのである。すなわち、将棋の持っているゲームとしての魅力の他に将棋を通じて作られた世界の魅力があるといえるのではないだろうか。